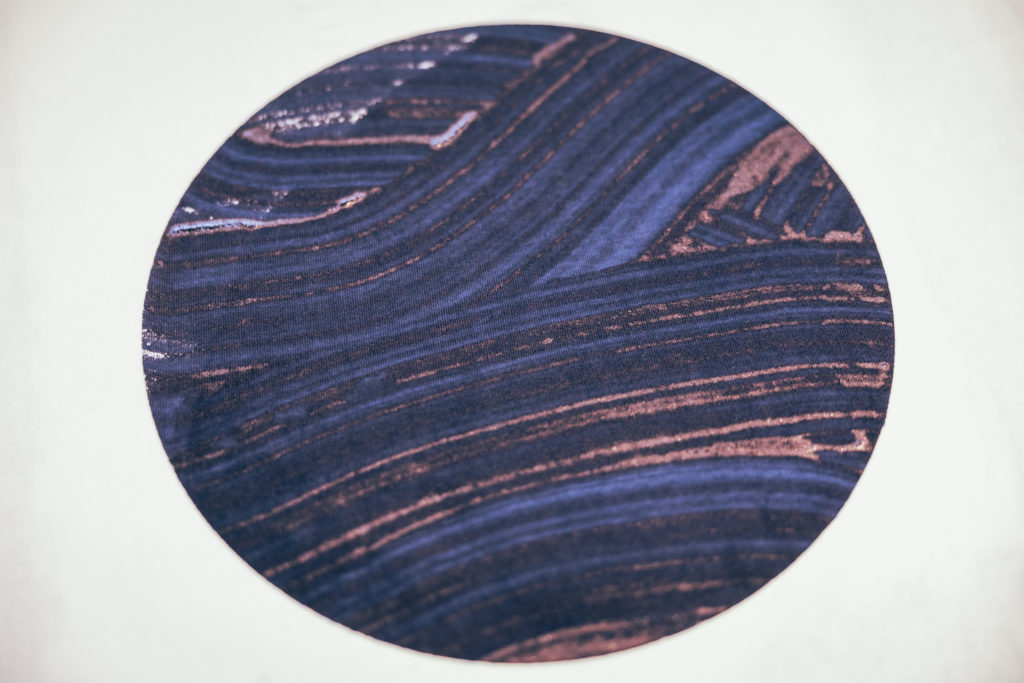【レポート】GRAND2022
たった2日間の〈GRAND2022〉展、ご来場いただきありがとうございました。
工業的な基盤から、文化的なものへの波及というテーマで挑んだ郡上のシルクスクリーン世界。しばらく、展示内容を振り返っていきたいと思います。
========================
今回の展示では工業的なものへのオマージュとして、単管パイプと(鋼管)と合板で、展示壁をつくるという建設現場の仮設小屋がイメージされていました。
そのため資材と展示物は、郡上からトラックとハイエースの2台で運んだのですが、出発して7時間後、都内に入るあたりで都市高速が地下にもぐった途端、スマートフォンのナビが停止し、私たちはどうやら会場のある池袋ではなく、東に大回りしているようでした。そうして地上に出てみれば、そこはかのレインボーブリッジ。
東京湾に浮かぶ摩天楼、全方位にビットのように、綺羅星のようにまたたくビル群の窓光を一望して陶然としましたが、谷の深い奥美濃・郡上にいると、同じ日本にこのような電影都市があることをまったく意識できないものです。
郡上藩江戸蔵屋敷は、江戸時代に郡上の藩邸および蔵屋敷があったことを踏まえた、現代の蔵開き、東京での交流イベントを企画主催しているのですが、あらためて東京でやることの洗礼を、この夜景に受けた気がしました。
おそらく私たちは、泥くさいことを、この郡上の薫りや気配、清らかな水やそこから蒸留されたもの、濾過されたものを持ち寄ろうとしているのでしょう。今回のシルクスクリーン作品たちも、どこかそうしたナマ感、風土の足あとが残せたら、と感じていました。

NEUTRAL COLORSと上村考版の制作
郡上のシルクスクリーンの世界をアップデートさせる試み、GRAND構想は、出版社のNEUTRAL COLORS(以後NC)との出逢いによって生まれました。なかでも手刷りのスクリーン印刷は、版を移動させれば、7メートル以上にもなる神社の幟なども刷れるグランドな特性が驚きでした。かつ製作できる最大の版サイズは2m×4mもあるらしく・・・。

今回も一度で刷り切れる大きさを表現するために、展示壁となる3×6サイズ(910mm×1820mm)の合板に、「GRAND」というロゴデザインを担当したNCのデザイナー、加納大輔さんに、ロゴの伸縮・反復展開された図版を制作してもらいました。
スクリーン印刷の現場となった郡上の〈上村考版〉では、上村佑太社長による刷りと、上村均会長のフォローにより、一色刷りの合板と、マットやラバー、レジューサーや蛍光色など、水性インクによるカラー見本のような合板作品に仕上げられ、赤と青のグラデーションや、1回から9回刷りまでの、刷りの行為によるテクスチャーの違いを見せるプリント見本としても完成しました。
こうしたNCのスクリーン印刷技術へのワンダーな感覚を見せるのが、展示入り口の導入です。「GRAND」というロゴが、ただ告知宣伝用のデータ上のロゴであるのではなく、全身を使ってスキージー (ゴムへらのような刷り道具)でサーッと刷られ、そして版を合板からはがした時に、初めて立ち現れてくる「GRAND」性だったことは、刷ってみないと私たちも分かりませんでした。
これらを現場で目の当たりにした時、東京への往路で遭遇した夜景以上に、目が覚めるような気持ちがしたものです。それはからだの営みで引き伸ばした「GRAND」であり、合板に染み込みながら、合板にノリ、それでも合板の木目がうっすら見えるというインクの皮膜の美しさでした。
「GRAND」というコンセプトが、プリントという行為に投げ込まれることで、身体実感とともに浮かび上がってくる。この私たちが得た大きなよろこびは、予定されていた全壁面へのプリントに加え、NC合板作品を展示の導入に位置付けることになったわけです。
ハンドプリントとデジタル孔版印刷機「リソグラフ」
NEUTRAL COLORS(以後NC)による展示監修は、導入に続いて内側の展示壁に続きます。そこでは、郡上のシルクスリーンの歴史をまとめた「HISTORY」と、スクリーン印刷工房12社への取材を敢行した江戸蔵案内人・井上によるテキストが、NCがリソグラフによって刷り出したA3プリント、それぞれ12枚にまとめられていました。

「HISTORY」のベースになったのは、江戸蔵記事でも度々紹介してきた高垣良平さんによる『郡上スクリーン印刷伝』(ROFLO DESIGN)。イラストもお借りして、ガリ版の原紙で成功した事業家塩谷広五郎と、シルクスクリーン印刷機とインクの研究開発者・菅野一郎の出逢いにより生まれた「グランド印刷機」。そして、郡上八幡に作られた「グランド印刷研究所」で養成された卒業生が全国で工房として独立する流れ。ゆえに郡上では今も20社以上のスクリーン印刷工房が健在で、お互いの仕事を助け合ったり、回し合うような地場産業として生き続けてきた経緯が踏まえられました。
特に郡上の工房は、ハンドプリント=手刷りが主軸です。2000年以後は、半数以上の会社がアパレル、衣服への印刷を主軸としていることが判明しつつも、工房それぞれに特性や得意なことがあり、各川筋に必ず10メートルから20メートル以上の長台を工場に据えて、木札や絵馬、提灯やのれん、Tシャツや、紙やビニールなどに実にアナログな手刷りを続けているのです。もちろんスクリーン印刷機械とも共存しています。
NCが今回の展示で使ったリソグラフも、一つの機械の中でデータから製版を行い、一色あるいは2色ずつ自動で刷り出すというデジタル・スクリーン印刷です。やっていることは、開けた穴にインクを通す孔版印刷なので、手刷りでやっていることを自動機械化したものといえます。これがやっぱり落ち着いた赤と青や、青と緑の2色使い、あるいはそれを重ねた色を足した3色使いになっていて、実にしっとりした風合い、ざらつきやあたたかみのある手作りZINEをめくる感覚なんですね。

NCが「レーザープリントされたものをパネル展示したくない」と言っていたことも、展示されてみて腑に落ちるようでした。手作りと機械の間を行き来しながら、GRANDという世界観にどういう生々しさと洗練を持ち込むのか。来場者もまた、デザインと印刷の関係をあらためて問い直すように、1万字近いテキストをじっと眺めていたのが印象的でした。
生きることは濁っていくこと

郡上に移住された絵本画家の阿部海太さんは、森羅万象と少年少女の生命観を、暗く明るく描き出すアーティストです。日本各地のセレクト本屋さんでは、必ずと言っていいほど見かける絵本を個人的に知っていた後、友人となった私(井上)は、シルクスクリーン作品を作るなら、阿部海太君に依頼しようと考えていました。
また絵を描く台紙は、こちらで美濃和紙と決めていました。郡上の隣である美濃の風土と手作業から生まれる和紙は、グランド印刷の前身事業「ガリ版」の謄写版原紙にも使われていたもの。特に、美濃和紙職人である千田崇統さんが麻と炭を混ぜて漉いたものや、楮と真菰を漉いたものなどの、大地か土壁のような迫力と奥行きは、「漉く」「描く」「刷る」が、一連なりになるための土台として欠かせなかったのです。
さて、ふだんは油画で制作する海太君から、スクリーン印刷を掛け合わせたときに何が生まれるのか、に興味がありましたが、やはりお題が必要ということで、私は郡上のいくつかの「湧水地」に彼を連れていきました。スクリーン印刷は版についたインクを洗うのに、大量の水を必要とするため、各川筋に工場を構える印刷会社は、山水を引き入れているところが多いのですが、やはりその水の出どころを見せて、どんな原画を仕上げるかを見守りたかったのです。
そこでの海太君の反応は、とても正直でした。「湧き上がる水は、地表の出来事で、その奥にもっと知らない世界が広がっているはず」「こんなきれいな水を描く自分は想像できない」。移住された古民家に下水処理がないため、生活排水は全てそばの川に流入する生活では、洗剤や流すものにはどうしても気をつけざるを得ない。ところが、どこまでいっても私たちは、美しい湧き水が流れる川を濁らせてしまう存在だろう、と海太君は語ります。
海太君は、その人の営み、濁りのプロセスを作品化するために、原画を1枚描くのではなく、3つのピースを描くことで、3版を刷り重ねた時に、一枚のシルクスクリーン作品が完成するという方法を思いつきました。しかしながら、誰も完成品を見たことがないわけで、上村考版での印刷日は緊張と不安に満ちたものでした。ここで活躍したのは工場長による色テストでした。2種類の和紙に対して、それぞれトーンの違う3色の色見本を刷って提案してくれることで、原画ピースとは違う、和紙における濁りのゆくえを探ることができたわけです。

水をテーマに、和紙に刷るというプロセスは、自ずと水性インクを選ばせ、原画ピースの再現ではなく、にじみや浸透、紙の伸縮も肯定するという気持ちで臨みました。一色ずつ刷り上げてドライヤーで乾かすたびに、まるで水を得た魚が、深いところに潜ってとどまるように、インクが和紙にすうっと吸い込まれて、色は淡く変化し定着していきます。
そして3色を刷り上げて乾かした作品の完成度には、感動以上に安堵の気持ちが強かったことを覚えています。水と血と土のはねあがる3枚のドローイングが、シルクスクリーンによって刷り重なり、未知の生き物となって一枚の紙におさめられていることに、暴れ川を治めたようなホッとした心地だったのです。

東京での「GRAND2022」展でやろうとしていたことに確信がようやく生まれたのは、この「水・血・土」が完成したことによってでした。このゆらゆらとした濁りのプロセスは、私たちをシルクスクリーンの奥へと誘う、洞窟壁画であったのかもしれません。
原画を開放するシルクスクリーン版画
シルクスクリーンの特徴である一色ずつの刷り重ねに加えて、もう一つ見せたかった魅力が「刷り分け」でした。江戸時代に大流行した浮世絵は、絵師・彫り師・摺り師に分業化されていた一大出版物でしたが、例えば北斎が描いた郡上の「阿弥陀ケ瀧」は、同じ版でありながら、崖の色や滝の裏の藍のムラなどを意図的に変えて摺り分けていたことが分かっています。
北斎が、原画を描くだけでなく、彫りも摺りもやる類まれな絵師だったからかもしれませんが、もともと郡上のスクリーン印刷業界には、絵を描いたり、デザインに優れて関心の高い人が多いことが取材を通して分かり、原画を印刷職人が自由に刷り分けるというチャレンジを行いました。
まず原画は、郡上八幡が誇る画家・水野政雄さんにお願いして、スクリーン印刷によって色分け展開をしてみたい旨の諒解をいただきました。「水」がテーマだったことから作品は「川のなかまたち」をNCの加藤さんが選出。オオサンショウウオを中心に、マスやアマゴ、カワゴイやウナギ、アカザスにクロイカ、ドジョウやチチコがくるくると泳ぎまわっている絵です。遠近法よりも、生き物の雰囲気や土臭さを大事にする水野さんは、スクリーン印刷も「味や手跡が感じられる」として、楽しみにしてくれていました。

印刷は、この道40年以上の別府スクリーンさんと、2020年に独立したAcid Drug Storeの井上奈々江さん。まずは、別府さんから分版に絶大な信頼が置かれている奈々江さんが、製版を行います。分版といっても、原画の完全再現ではなく、3〜4版と決めて、どの模様や輪郭を版分けしていくかは、センスが問われる仕事。この分版が甘いと、同じ色がそこかしこで隣り合ってしまい、色分けされた原画のメリハリは失われてしまいます。
さて、印刷に入ってみると奈々江さんは、得意とする蛍光インクやシルバーラメ、また輪郭の二重印刷や、一版に2色を使うマーブル仕様、無色に近い染み込みインクなど、あらゆる手管を使い、4種類のプリントを仕上げました。これに対して、別府さんは、シャツに使うような隠蔽力のあるラバーインクのみを使用し、色も全て落ち着いたシックなあじわいで4種類のプリントを仕上げてきたのです。
当初は2パターンずつできればくらいに思っていたのですが、若手の刷り師が4つやってみました、と上げてきたら、それに負けじと先輩が4パターン上げてきたことに、予想外の興奮を覚えつつ、展示のスペースが足りるかな、とヒヤヒヤしました。なんとか間に合わせた合板7枚の展示壁では、あらためて水野さんの原画の水彩を堪能するとともに、スクリーン印刷でしかなしえない色彩の開放に爽快感を覚えるものでした。
そして、あのジブリを1人で超えているような水野政雄さんの作品が、和紙であれ、布であれ、どんな媒体にも生き生きと写し取られるのを目の当たりにして、もっと多様なプリントの可能性があるのだと感じずにはいれられませんでした。

まとめ
2日間の「GRAND」展のなかで、終始注目を浴びていたのが、「プリントデモンストレーション」でした。上村考版のグラフィックデザイナー上村大輔さんに依頼した、Tシャツへのプリントは、常に即興的に仕上げられ、時に観客への注文も聞きながら、そのまま販売され続けました。

なかでも目をひいたのは、版のデザインだけではなく、刷るというアクションの豊かさでした。スクリーン印刷で使われる刷り道具・スキージー のゴムへらを刻んでわざと刷りムラを出したり、自由にスキージーを回転させて刷りアトを見せるなど、受注がメインの業界では考えられない、と同業者からも驚嘆の声があがっていました。
また刷り下ろされるTシャツ自体を折り重ね、絞りのようにインクがのらない部分をわざと作り出して刷る、版を自由に移動させてあちこちに刷る、インクがにじむように先に水で濡らしておく、刷った後に水でぼかすなど、あらゆる手法をその場のテンションと創意で生み出していくというエネルギーの渦が、展示会場の中心で巻きおこっていました。
こうしたアーティスティックな創造性がスクリーン印刷と出逢った時に何が起こるのか、そこに今後の「GRAND」の目的の一つがあるといえます。今回の、ミノグループの永瀬真一社長のコレクションをお借りして展示した、アンディ・ウォーホルの「キャンベルスープ」(ミノグループが公式依頼を受け制作)や、画家井上公三によるスクリーン版画なども、そうしたアーティストと印刷手法との出会いによって生まれた革新的な作品であることが分かります。

郡上藩江戸蔵屋敷では、こうしたアーティストとスクリーン印刷工房との出会いの創出のために、来年の2月に「アーティスト×工房ツアー」を行う予定です。グランド印刷文化とでもいうべき郡上の地場産業が、さらなるマッチングによってどのような表情を露わにするのか、私たちの挑戦と探求はこれからが始まりといえます。
あらためて、WACCA池袋「GRAND2022」にご来場いただいた方々、展示にご協力いただいた皆様、まことにありがとうございました。次章では、郡上のスクリーン印刷工房を紹介してまいります。
========
〈訂正とお詫び〉
「GRAND2022」の展示テキスト【HISTORY】欄におきまして、現ミノグループの創業者塩谷広五郎の甥である「永瀬英一」様の表記が「永瀬一郎」となっておりました。謹んでお詫び申し上げます。